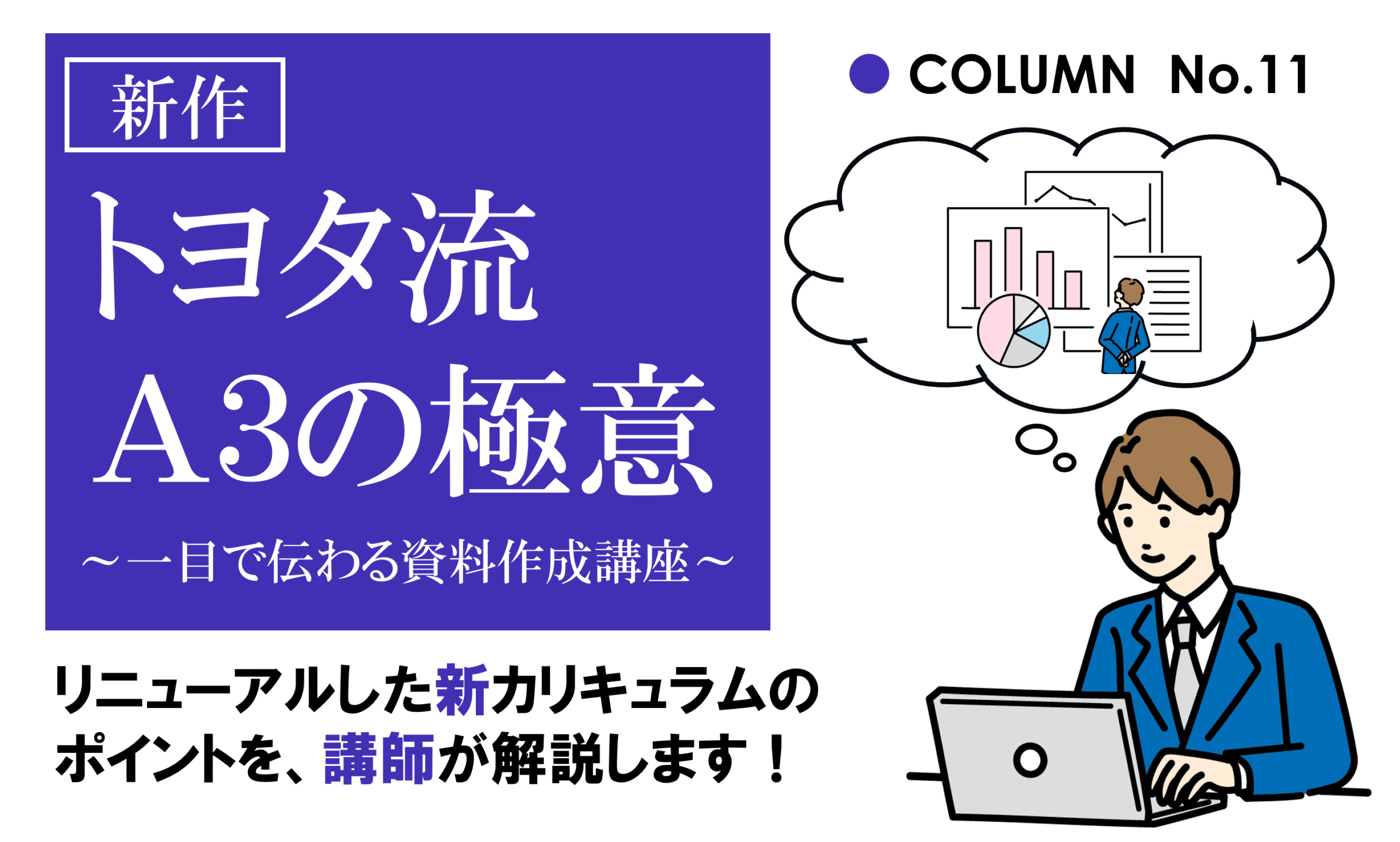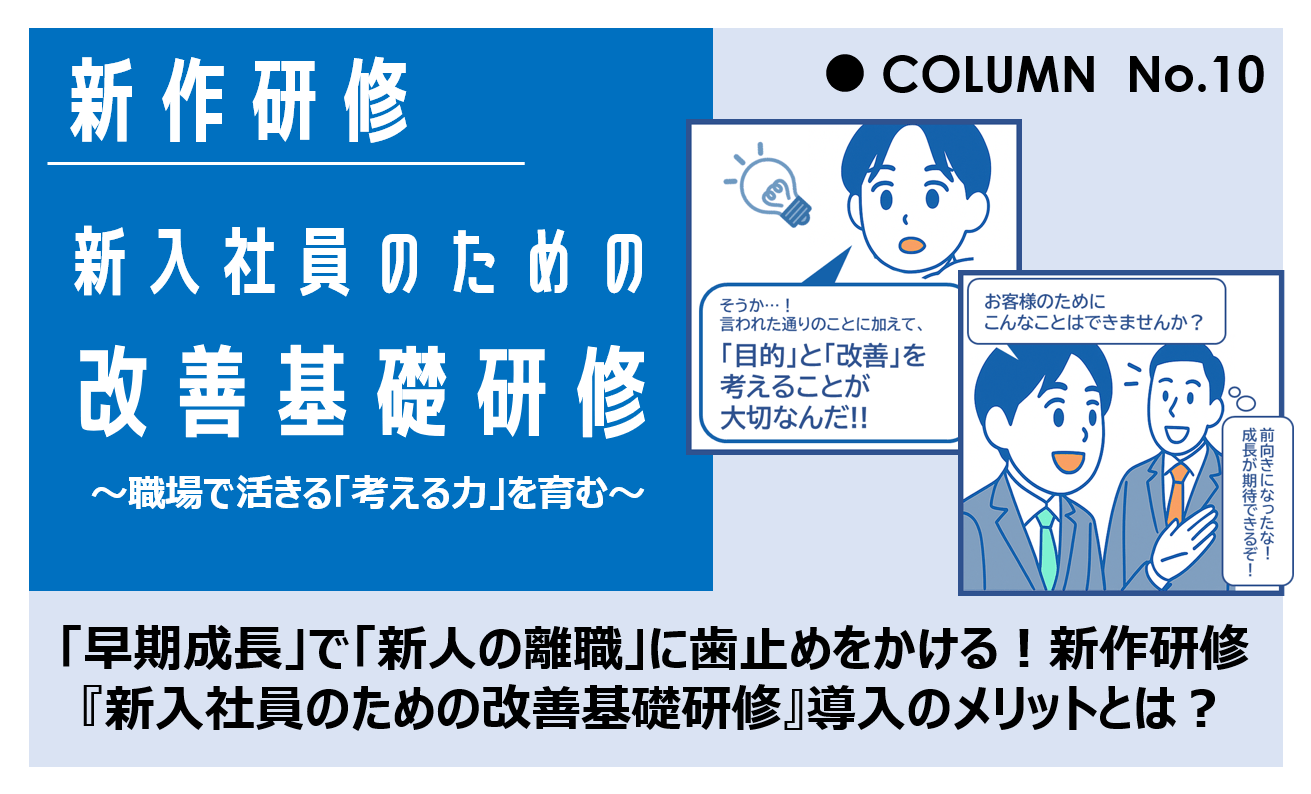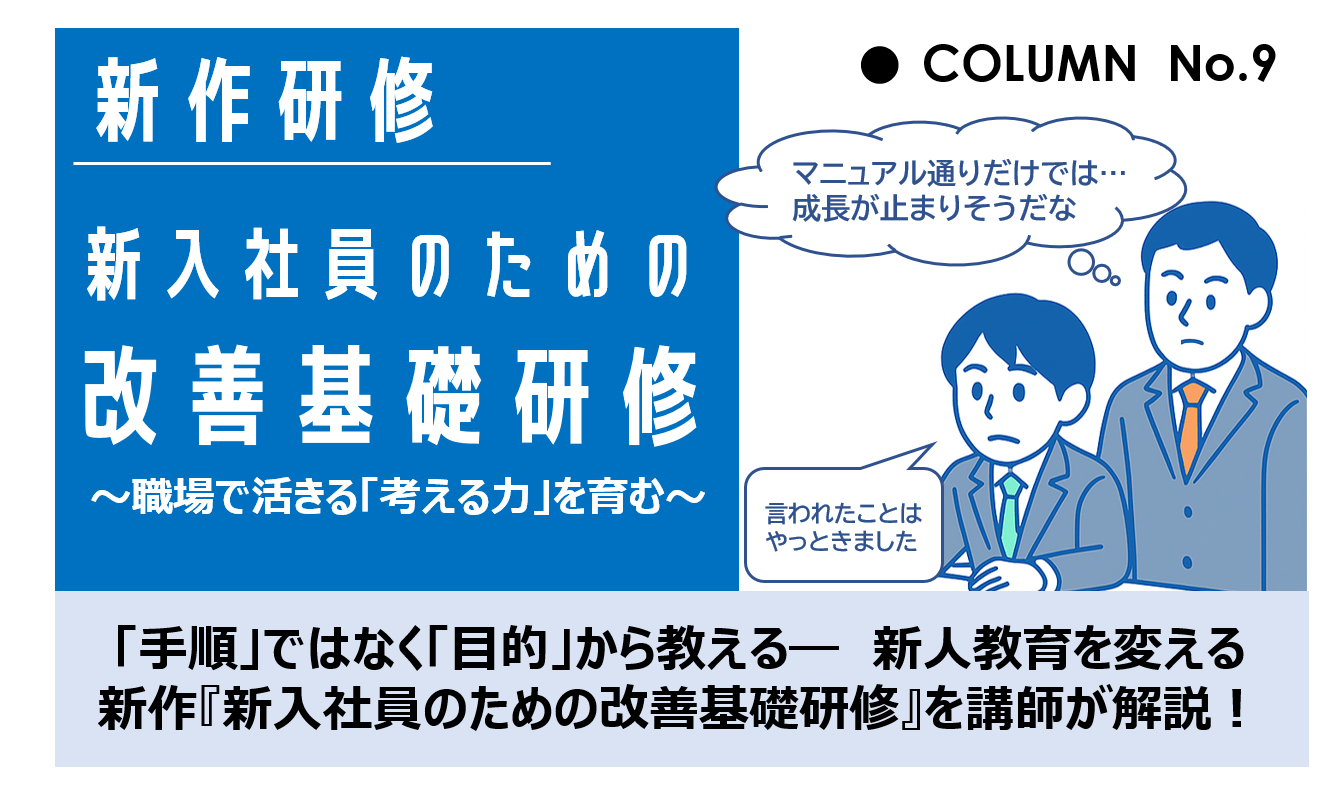対症療法ではなく原因療法を。トヨタ流研修を提案する若手営業社員の思い
カテゴリー:
社員インタビュー
キーワード:
人材育成問題解決社員インタビュー課題解決風土改革
2025.07.23

トヨタ流研修をはじめさまざまな研修の提案営業を行っているトヨタエンタプライズ広域営業部の若手社員インタビューです。研修のメリットや導入事例について聞きました。
「人材育成やキャリア支援のために社員研修を行っても、社員はやらされ感があり、なおかつ成果も出ない…」とお悩みの人事担当者の方もいることでしょう。もしかすると「今抱えている問題を解決するために、どういった研修が必要なのか」について、今一度問い直してみるのが良いのかもしれません。根本から問題を解決したいお客様には、トヨタ流の考え方を活かした社員研修をおすすめします。
この記事では、実際にトヨタ流研修をはじめとしたさまざまな研修の提案営業を行う若手社員の二人に、研修のメリットや導入の成果などについて話を聞きました。

<プロフィール>
S.Tさん(広域営業部 営業室 営業グループ)
2023年度新卒入社。趣味はバスケットボール観戦。
Y.Oさん(広域営業部 営業室 営業グループ)
2023年度中途入社。趣味は卓球、ロードバイク、ランニングなど
◆粘り強く、ポジティブに。お客様の課題に向き合う若手社員たち
「お客様と課題に向き合って伴走しながら、どのような層を対象に研修していくのかについてしっかりとご提案できたことは、とても印象に残っています」とS.Tさん(以下Tさん)はさわやかな笑顔で語ります。
彼は、2023年度新卒入社の社員。みずからを「ポジティブであきらめない人間」だと評します。バスケットボールなどのチームスポーツに長く取り組み、チーム一丸で奮闘する経験を積んできたこともあって、社会人になってからは、人の役に立ちたいとの想いがいっそう強まったとのこと。
入社して数年経ち、後輩社員の育成も求められていることに強い責任感を持って自走している様子。そうはいいながらも社内外で何かと愛される(イジられる?)、天性の愛されキャラです。

一方、「お客様からは、今まで考えてなかった自組織の課題について目を向けることができた、という感謝のお言葉をいただきました。『聞くだけでなく、受講者に考えさせる研修なのがすごく良かった』とも」と嬉しそうに話すのは、同じ部署のY.Oさん(以下Oさん)。
2年前に中途入社した彼女も、体を動かすことが大好きです。卓球の社会人クラブチームに所属し、毎週のように練習や試合に精を出しているのだとか。トヨタグループの駅伝大会にも参加しているというスポーツウーマンは「雑草のように粘り強い人間だといわれます。ガッツだけはあります」と、話しぶりから謙虚で真面目そうな一面が垣間見えました。
また、推しのアイドルの話をしはじめると止まらないところに、彼女の「誰かを支えたい気持ち」の強さが表れています。
◆営業活動にも日々カイゼンを
トヨタ流問題解決では、「現状」と「あるべき姿」のギャップを「問題」と捉えます。
「お客様は何かしらの問題を解決したいから、問い合わせくださっています。だからこそ、こちらが『この研修を』と思い込みや決めつけで、一方的に提案してしまわないようにしたい。お客様のお悩みをしっかりとヒアリングして一緒に課題に取り組むよう、傾聴のスタンスを心掛けています」(Oさん)

では、彼らのような営業社員が考える、トヨタ流研修の強みとは何なのでしょうか?
Tさんは「トヨタで実際に現場を見てきたOBを中心とした講師と、トヨタ製造現場の考え方を事務系などさまざまな仕事に活かしていただける実践的なカリキュラムや演習」を挙げます。
Oさんも「研修の成果というのは、客観的にわかりにくいと思う」とした上で「トヨタ流研修はトヨタの現場で実際に行われている考え方を活かした内容なので、説得力がある」と力強く語りました。
とはいえ、奥が深いのがトヨタ流研修。二人も「自分たちも日々、カイゼンの気持ちを忘れずに取り組んでいる」のだそう。「自分自身が知識として理解したと思うことは多いのですが、問題解決の8ステップひとつにしても、お客様に表面的に説明するのではなく理解してもらおうとすると、一筋縄ではいかないです」と告白するTさんに、Oさんもこう賛同します。
「お客様に魅力を感じてもらうためには、自分もわかったつもりではなく、もっと深いところで理解していかなければ…」
彼らはまだまだ、現状に満足していません。自分たちのトヨタ流研修の強みの伝え方には、カイゼンできる余地があるのだと――。
そう、自分自身の課題について「なぜ?どうして?」と問い続け、PDCAを回す習慣が身に付いているようです。
◆大切なのは「実務に役立つ」ことと「目的意識の共有」
実際にトヨタ流研修を導入したお客様には、どのような反響や効果があったのかも気になるところです。
数十社を担当するTさんは、ある製造業のお客様から相談を受けたときのことを振り返ります。「課長クラスの方からのお問い合わせで、『経営層が会社全体の問題解決能力に悩みを抱えている』とご相談をいただきました」それまでは自社で社員研修に取り組んでいたものの、職層ごとにスポットで行っていたため、効果が表れにくかったとのこと。
「対症療法的にではなく、お客様が抱えている問題の原因を発見し、解決したいと感じました。社員の共通言語としての問題解決の考え方を学びたいとのことだったので、『問題解決研修 基礎編 ~8ステップと考え方~』を提案し、100名ぐらいの管理職の方々に受けていただきました」
研修後、社会人の大ベテランである管理職の方々に「ここまで深く問題解決の考え方について学べて良かった。今後は学んだことを実務に落とし込んだり、自分のチームの部下に教えたりするためにしっかり復習する」と言ってもらえたと、Tさんは嬉しそうに語ります。

Oさんも「社員の業務量が多く、残業時間が増えているのが悩み」とお客様から相談を受け、トヨタ流研修を提案しました。当初は希望者のみの受講だったのが「自分の普段の業務に落とし込んで、グループで考えて議論する演習」などの内容を高く評価され、「他の職層、特に若い社員全員にも受けてもらうべきだ」となり、毎年の定期開催が決まったのだとか。
なぜトヨタ流研修が評価されるのか。それは「即座に実務に活かせる」という受講者のメリットがはっきりしているからなのは、もちろん言うまでもないでしょう。
それに加えて「なぜ、この研修が必要なのか?」という目的意識が、二人のような営業社員とお客様との間で、しっかりと共有されているからなのかもしれません。
Oさんはいいます。「『社員の成長のために研修を実施したい』という会社側の想いと『忙しい業務スケジュールの中で、さらに研修を受講しなければならない』という受講者側の想い、この双方の認識が食い違ってしまうのが一番もったいない」と。
「だから、会社としても『会社は社員の皆さんにこれぐらい期待しています、だからこの研修を受けてもらっているのです』と受講者に意図や目的を理解してもらえば、受講者の皆さんも『自分もこんなに期待されているのなら、もっとがんばらなきゃ』と前向きに取り組んでくれるんじゃないかと。…そんなマインドがもっと浸透すればいいなと思っています」(Oさん)
二人は、多くの社員研修が対症療法的に行われてしまっていることを危惧しています。だからこそ彼らはトヨタ流の「なぜなぜ分析」を駆使しながら、お客様の組織が抱えている問題の真因を発見して、目的を明確にした研修を提案しているのです。
◆多様化する働き方の問題を真因から見直す
彼ら若手二人が、お客様から最近よく受ける相談は、「若手社員について」なのだとか。
「最近は『若手社員が受け身で困っているが、何か指導してハラスメント扱いされるのも困る。何をどこまで指導したらいいのかわからない』というお悩みをよく相談されます。若手社員にモチベーションアップ研修を受けてもらうのはもちろん、その若手社員が働きやすい職場環境も重要だと思っているので、職場風土の研修を提案することもあります」(Tさん)
「管理職の方々の『若手の育成に課題感がある』というお悩みを深掘りすると、実は上司世代・若手世代、双方のコミュニケーションの問題に行き着くことも。そんなときは、世代間のコミュニケーションを円滑に行うための「モノの言い方や伝え方」の研修などを提案しています。世代間コミュニケーションに関する課題は、私自身も「自分事」として感じる場面があります。上司世代・若手世代双方にとって最善な解決策を、研修でご提案していきたいと思っています」(Oさん)

今は、未曾有の人口減少時代。働き手不足や離職対策のほか、リーダー育成など、人事系のお悩みは決して尽きることがありません。一方で、働き方は多様化し、これまでの経験則がなかなか通用しなくなってきています。彼らは、社会人として大先輩にあたる人事・研修担当の方々が抱えるさまざまな人事的課題に、日々寄り添っています。
彼らは、これからどのように成長していきたいと考えているのでしょうか。 「当たり前のこととして、いただいたお悩みの解決のため、最善の提案ができるようにと心掛けています。さらにプラスアルファでお客様に喜んでいただけるよう、まだ言語化されてないこと、表面化してない問題までも汲み取りたいと思っています。人手不足や人材採用・育成についての問題を抱えている人事系のお客様のため、もっとその分野の知識を身に付けていきたい」と、真剣な面持ちで語るOさん。
一方のTさんは「自分は…貫禄を付けたいですね」と茶目っ気のある笑顔でいいます。これは単なる冗談ではなく、心身ともに信頼される人間になり、お客様からもっと頼りにされたい――という彼なりの正直な表現。Tさんは最後に、こう締めくくってくれました。
「どんな問題でも、とにかくまずは相談していただきたいです。問題の真因が明確になっている方々はもちろん、現段階で表面化している問題でも、どんなことに課題感をお持ちか、どのような組織を目指したいか、お話を聞かせてください。お客様と一緒に伴走しながら、背景にある真因を掘り下げて、それに対する最適な解決策を提案していきたいですね」

対症療法的な対策ではなく、そもそもの「目的」と「あるべき姿」にこだわる。その上で、問題を確実に解決する「考え方」を養い、実践していく。それがトヨタ流のカイゼン(問題解決)です。
広域営業部の二人は、これからもさまざまなお客様の問題解決のために、東奔西走していきます。そう、彼ら自身もまた、日々地道なカイゼンに取り組みながら。

写真:髙橋学(アニマート)